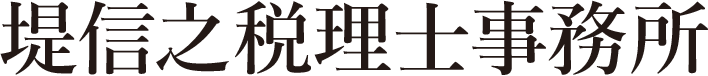相続のご相談
相続税とは
相続税は、法定相続人が相続財産を相続した場合、または遺言により相続財産の遺贈を受けた場合に課税されます。
法定相続人とは
民法では、相続人の範囲が決められています。下記の表のように、順番が決まっており、これを、法定相続人といいます。
相続人の相続順位
第1順位 子と配偶者
第2順位 配偶者と直系尊属
第3順位 配偶者と兄弟姉妹
相続財産

・プラス財産
<民法上の相続財産>
- 土地・建物
- 借地権
- 現預金
- 有価証券(上場株式・自社株・公社債・投資信託 etc)
- 貸付金・売掛金
- 特許権・著作権
<贈与により相続財産とされるもの>
相続開始前3年内の相続人等に対する暦年課税贈与財産
相続時精算課税制度により贈与された財産
贈与税の納税猶予制度により贈与された非上場株式
<みなし相続財産>
死亡保険金(生命保険・損害保険)
死亡後3年以内に確定した退職手当金(一定額を除く)
生命保険契約に関する権利
・マイナスの財産
借入金・買掛金
未払いの所得税・固定資産税等・住民税・医療費・水道光熱費など
預かり敷金・保証金
相続税は、相続財産が一定額を超えた場合に発生します
相続税の「かかる」、「かからない」は、相続財産の合計に対しての基礎控除額の大小によって決まります。
相続税法には、さらに以下の基礎控除が設けられています。
基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続の手続きについて
相続の放棄又は限定承認は3ヶ月以内までに済ませましょう。ただし、3ヶ月では決められないという場合には、家庭裁判所に申し立てると延長することができます。
被相続人の1/1から亡くなった日までの所得に対して、所得税の確定申告を行います。申告期限は、亡くなった日から4ヶ月以内です。
なお、1/1から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合であっても、申告期限は3/15ではなく、亡くなった日から4ヶ月以内となります。
納めた所得税は債務控除の対象になり、還付の場合は相続財産となります。
相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内となっています。
申告期限までにやらなければならないことは下記のとおりです。
- 相続税申告書を所轄税務署に提出するとともに納税をします。
- 金銭納付が困難な場合には、延納申請または物納申請をします。
※延納申請書及び物納申請書は、相続税申告書と同時に申告期限内に提出します
相続発生前から発生後まで親身にサポート
相続・事業承継における、難解な税務処理にも明るく様々な事例も熟知。あらゆるご相談を解決に導きます。